ダムドという名の深き森 -episode3
text by Tsuneglam Sam/YOUNG PARISIAN
前回、2nd.アルバムに行き着かずというまさかの展開に自分で書いて自分でびっくりしたが、続けよう。
歴史を追うと、1977年の後半、DAMNEDはアメリカをツアーした最初のイギリスのパンクバンドとなるのだが、そのスピーディーなパンクロックは西海岸の初期のハードコア・パンクに大いに影響を与えることとなった。
同年8月、ルー・エドモンズがセカンド・ギタリストとして加入。デイヴ・ヴァ二アン、ブライアン・ジェイムズ、キャプテン・センシブル、ラット・スキャビーズ、そしてルーの5人編成となったTHE DAMNED。

このメンバーで2nd.の制作に入るわけだが、彼らがプロデューサーとしてオファーしたのはなんとシド・バレット! 当時すでに隠遁者と化していたシドからのOKはもらえたものの残念ながらこの夢の組み合わせは実現せず、代わりにPINK FLOYDのドラマー ニック・メイソンが手掛けることとなった。こうして2nd.アルバム『MUSIC FOR PLEASURE』は1977年11月にリリースされたのである。

通称“よくない二枚目”の名を欲しいがままにしてる本作はリリース時は酷評の嵐。そして今も再評価は高まらないままである。まぁたしかに1st.と比べてインパクトに欠けてしまうのかもしれないが、曲自体は決して悪くないしそこまで酷い作品ではない。私は大好きなアルバムだ。バーニー・バブルス デザインのジャケットもいいしね。
まず、ここで再評価したいのは、オリジナル・パンクである彼らはパンクロックにしがみつく気なんてハナっからなく、実験精神に溢れ、自らが愛してきたガレージ/サイケやSTOOGESとMC5の衝撃再構築を1st以上に試みようとした点である。サイケデリックロックや60’sのビートをヴィンテージな懐古趣味の音ではないモダンな音でリモデルするのがDAMNEDのスタイルだ。この姿勢は後の『BLACK ALBUM』、『STRAWBERIES』以降現在にいたるまで一貫して貫かれている。
さて、この連載を読んでいただいてる方々にはもうパンクがオールドウェイヴと地続きであったことはわかっていただけてるだろう。だが、それにしても“DAMNEDとPINK FLOYDのメンバーが一緒にアルバムを制作した”という事実には何十年たっても「え、なんで?」という思いが消えないかもしれない。
そもそものキッカケはというと、DAMNEDが当時契約していた音楽出版社はPINK FLOYDの作品も取り扱っており、社長のピーター・バーンズはPINK FLOYDと親しかったことも要因だ。そこで特にキャプテンとブライアンが大ファンだったというシド・バレットにまずオファーしたが実現せず、結果落ち着いたのがニック・メイソンだったという成り行き。

デイヴ・ヴァ二アン
「とにかく目新しいことがしたかった。シド(・バレット)とならそれまでとは違うアプローチが実現できそうな気がしてね。DAMNEDが持ってるRAWな部分やエキサイティングな面はもちろん残しつつ違うやり方を試したかったんだよ。そういうことが実現できそうなプロデューサーとして思い浮かぶのは、当時はシドくらいしかいなかったんだよね。DAMNEDとシド・バレットの組み合わせならきっと興味深いものが生まれるだろうって気がして」
デイヴは以前私の行ったインタビューでそんな風に語っていたが、「シドがダメならニックでも」となったのは何故だったんだろう。PINK FLOYDのメンバーという超ビッグネームではあるがニック・メイソンとは何者か。彼がDAMNEDをプロデュースする前後はどんなアーティストを手掛けたのかを調べてみることにした。

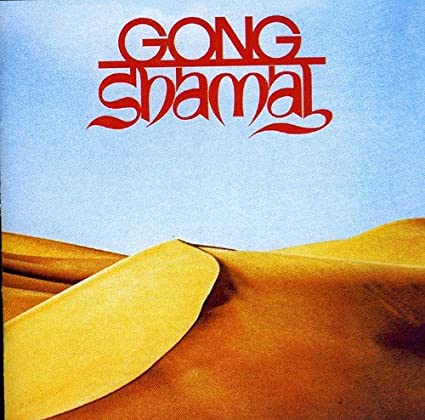


なるほど、これなら安心してDAMNEDがニックにオファーしたのも不思議ではない。というのもキャプテンは大のカンタベリー好き。DAMNED以外はカンタベリー・シーンの作品ばかりではないか。(因みに「カンタベリー」とはイギリスのカンタベリー出身者を中心とするプログレッシブ・ロック系のバンド、ミュージシャンの一群による音楽を指すもの。ザックリいうとプログレのサブジャンルではあるわけだが、ものすごく雑に説明するとサイケ感もあり、シンフォニックで退屈なプログレとは非なるものです。)
若き日のキャプテンは SOFT MACHINE、 EGGなどのカンタベリーのレコードを熱心に聴いていたようであり、ラットにしてもCARAVANとGONGが大好きだったようだ。キャプテンが言うにはCARAVANのもの凄いファズオルガンが大好きで、そこからヒントを得て『 I Just Can’t Be Happy Today』(『MACHINGUN ETIQUETTE』収録)が生まれたとのことである。
あ、みなさん、ついてこれてますか?
この連載の“深き森”ってのは私が以前かなり愛読してたレコード・コレクターズ増刊 『英国ロックの深き森』からとったんですけど、本当にそんな内容になってまいりました。
でもね、DAMNEDを語る上でプログレはかかせないんですよ。『Fun Factory』にはKING CRIMSONのロバート・フリップが参加してますし、最近知ったことですが『Rabid (Over You)』(80年)でシンセ弾いてるのはSLAPP HAPPYのアンソニー・ムーアだったりもします。音楽の実験性を追求する上でプログレは避けて通れないんですよ。だから、当時のパンクスがプログレなんてクソだって言ってたのを全部鵜呑みにしちゃいけません。 あの偉大なるパンクロッカーがTシャツに書きなぐった「I HATE PINK FLOYD」に惑わされすぎではないでしょうか。だって、私が以前そのお方に電話インタビューした際、「I HATE とTシャツに書きなぐったPINK FLOYDは実は嫌いじゃなかったそうですが、ほんとですか?」と問うてみたところ、
「その通り!!世の中に対する皮肉を身を以て表したかったってだけだよ。わははは!」
とのお言葉をいただいたのです。つまりはDAMNEDの「HELP」と同じく権威への挑戦なのですよ。
とはいえ、パンクは“退屈な”プログレにはやはり牙を剥くことは忘れちゃいない。キャプテンは「プログレは好きだが20分のドラムソロは好きじゃない」 「パンクはYESとGENESISをぶっ潰すのが仕事だったけど、カンタベリーは好きだった」と語る。 つまりはプログレやカンタベリー、サイケの実験性を愛し、そこから退屈な部分を取り除き、時代にあわせてスピードアップさせ、それになによりも“攻撃性”を加えたのがこの2nd.アルバムだったのではないだろうか。よくよく聴きなおしてみれば、本作のオープニングを飾る『Problem Child』などはまさにPINK FLOYDの初期のナンバー『Arenold Lane』や1stアルバム一曲目『Astronomy Domine』をパンク化したようなナンバーだ。
その他にも、TELEVISIONを皮肉った『Idiot Box』があったり、サックスにLol Coxhillを迎え入れた 『You Know』や『Alone』のように前作以上にSTOOGESの影響を隠さずにやってのけたナンバーなどもあり、曲単位で聴いていけば実に興味深い内容のアルバムなのである。
多くのパンク原理主義者は本作をダメにしたのはニック・メイソンのせいにしたいだろう。たしかにニックはDAMNEDのサウンドをどうまとめていいかわからないでいたと思うし、あの個性豊かなラットのドラミングを活かすことにも失敗している。だが、皆の期待(?)に反して当のメンバーはニックのことを悪くは言ってない。ブライアンはとにかくレーベルからせかされて準備不足だったことを強調するし、キャプテンもメンバー間のコミュニケーションがなかったと語る。デイヴもぎくしゃくしてたバンド間の話ばかりでニックのせいにはしていない。それどころか、 キャプテンはニック・メイスンをいい奴だと評し、彼とジャムセッションした楽しい思い出を語っていたりするぐらいだ。一方でニックの方も後にこの仕事を「とても楽しかった」と述べ。PINK FLOYDがドラムをセットアップする時間よりも早く4曲を録り終える彼らのやりかたに大いに感銘をうけ、それはPINK FLOYDのアルバム『ANIMALS』の制作に影響を与えたとの発言も残している。

まとめると、音楽的な意欲は十分で、1st.とは違う実験的な作品に挑戦したかったが、時間もなく中途半端な出来となったというのが本作なのだが、たしかに曲の構成は1stより複雑なことをやろうとしたものの整理しきれなかったという感はいなめない。それでも「サイケデリックなパンクアルバム」を夢みたキャプテンの気持ちは汲みたい。これがシド・バレットと組んだら果たしてどうなっていただろうか……それを想像するのはなんとも幻想的なロックンロールドリームではあるが、この時期のシド・バレットの状態を考えたらそれはやはり難しかったのであろう。
DAMNEDは後にライヴでPINK FLOYDの『Arenold Lane』をカヴァ―しているのだが、キャプテンもシド・バレット・トリビュートライヴ(2007年)で『Astronomy Domine』をプレイしてるし、シド・ソロの『Octpus』のカヴァーも録音している。こんな風に初期PINK FLOYDの影響は彼らの音楽に色濃く混入しているのは間違いない。それがDAMNEDの音楽とうまく噛み合ってくるのはもう少し後になってからのお話だ。
さて、これはあくまで私の妄想にもとづく意見ではあるが、DAMNEDにとって目の上のタンコブは誰だったのか? それはSEX PISTOLSでもCLASHでもない。DAMNEDがやりたかった60年代の音楽をモダンに再構築し、プログレから退屈な部分を差っ引いて攻撃性を加えるという部分をうまく帳尻あわせ独自のサウンドとして放って成功していたバンドがいるのだ。
そう、それはTHE STRANGLERSである。

STRANGLERSの2nd.『NO MORE HEROES』は『MUSIC FOR PLEASURE』がリリースされる2か月前1977年9月にリリース。英国では2位まで昇りつめている。DAMNEDとSTRANGLERSでは脳裏にそのルックスが浮かぶと比較するのに違和感があるかもしれないが、両者はある種、音楽的なバックボーンや進化の方向性(サイケとヨーロピアン嗜好)が非常に近い。しかしセールスにおいても常にSTRANGLERSはDAMNEDの上を先をいっていたのだ。そんなことでやっぱり当時は比較されもして、このDAMNEDの2nd.はますます駄作の烙印を押されたのであった。

ここでルー・エドモンズについても書いておこう。ルーは後にダムドに一時期加入する男ジョン・モス(NIPS, LONDON, CULTURE CLUB)らとTHE EDGEというバンドを結成。これ不思議なことにちょっと中期DAMNEDにも通じる音楽性なので興味のある方は聴いてみてください。またTHE EDGEは女性ヴォーカルとともにJane Aire And The Belvederesというガールズパワーポップ・ファンは漏れなく好きそうなバンドとしてレコードをリリースしている。

その後のルーはTHE MEKONSでの活動も有名だが、なんといっても重要なのは86年から88年、そして2009年から現在にいたるまでP.i.Lに在籍していることを書いておかねばならない。P.i.Lではギター以外にもトルコやイランで使われる「サズ」という楽器などをプレイし、DAMNED在籍時には薄かった影を妖しく膨らませミステリアスな魅力を漂わせ続けている。

以上、述べてきたように2nd.アルバムは実はものすごい興味深きトピックだらけの作品だ。「『Don’t Cry Wolf』は最高だよね~」だけでは終われないんですよ。いくら駄作といわれようが、ダムドという名の深き森の住人にとっては彷徨いがいのありすぎるアルバムだ。つまりはこれぞ喜びの音楽……まさにMUSIC FOR PLEASUREだと言いきっておこう。
I HATE PINK FLOYDという言葉に扇動され、若者のための新たなロックンロールに走った世界中のバンドも尊いが、初期衝動のみにとらわれず、かつて好んだ音楽の影響を握りしめたまま新たな音楽表現に挑戦しようとしたDAMNEDの姿勢もまた尊いと言えよう。
続く。



-500x250.jpg)

