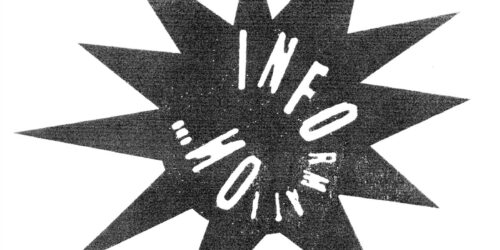Review-Kikagaku Moyo/幾何学模様-Kumoyo Island
text by Hyozo-ゴヰチカ
日本の2010年代インディシーン出身では数少ない、海外で成功を収めた5人組ロックバンドの活動休止前最終作。サイケバンドの最終作というのはどれもこれも凄いというのが定評で、どうしても身構えて聴いてしまうものだ。
ゆらゆら帝国の「空洞です」で聴ける孤独の果てのアフターグロウ寂寞感、ダモ鈴木脱退前Canの最終作である「Future Days」のような定位さえ異常なコラージュプログレ音響宇宙、そんなエクスペリメンタルな世界を想像して聴いたリスナーに対してどんなメッセージがぶつけられるのかと思えば、
「もな〜か、なかなかの〜」
と極めて間の抜けた脱力ぶり。曲名も「Monaka」だし。
実は日本語で彼らが歌うのは初めてのことだが、情勢的にもミュージシャンがついつい取り組みがちな「うぉぉ混迷する世界よ〜」のようなやや短期視点的なコンテクストを音楽から注意深く排除する潔さと、自分達の音楽を「Feeling good music」と簡潔に定義しているように、音楽することを純粋な喜びと捉え眉間に皺を寄せた表現を対外的に行わない一貫性が彼らにはある。
音楽家がサイケデリックな世界を他者と共有する場合は、あまりバッドな方向に行って欲しくないという欧米の空気のようなものも彼らの表現に影響を与えたかもしれない。
Carlos Ninoを感じる自然回帰サウンドスケープ「Effe」、Erasmos Carlosのカバーであり、アシッド100μg注入フォーク「Meu Mar」などはコロナ禍でやたらに称揚されたバンド内の遠隔ファイル交換だけでは生まれない生命への讃歌に満ちていて、現代日本人がこの方向に生命観を極めることは実は生き方のレベルで凄く難しいことを今更ながら実感。

A面は彼らの強みでもあるフォーキーな音色でチル&ネイチャーなカラーに統一されており、B面からややハードなテイストが見え隠れする。
前作の「Masana Temples」全曲を4分間に融合させたような「Cardboard Pile」は気鋭の作家葛飾出身の目まぐるしいPVも秀逸。
「Gomugomu」のPVで「かわいさ」が違和感なく取り入れられている柔軟さも、彼らが国内のグループで唯一KhruangbinやKing Gizzard & The Wizard Lizardなどと比肩されて語られる理由の一つでもあるように思える。
「Yayoi Iyayoi」で披露されるメロディアスな歌はWhiteberryの「夏祭り」さえ一瞬想起させるストレートなジャポネスク。私たちが普段ベタと考えてしまうことでさえ、グループの最終作でやることと思えばかえって胸に刺さる。

最後の「Maison Silk Road」はとても示唆的なタイトルのアンビエント。ゆらゆら帝国は「空洞です」というピュアネスの極みに到達したフォークロック曲でその幕を閉じたが、幾何学模様は全く異質な方法でピュアネスの極みへと至ったことがわかる。そして即興的に爪弾かれるシタールとピアノが名残を惜しむかのようにゆっくりと去っていき、この旅は終わる。

10年間にわたる果てしない肉体と精神の旅を繰り返したロックバンドの最終的な表明であり、メンバーたちの人生そのものが込められた非常に味わい深い作品。LPが手元に届くまではもうしばらくかかるようだが、6000枚のファーストプレスは早くも残り少なくなっているようだ。
あらゆる構造的理由もあり、日本人ロックグループがこの領域まで辿り着くのは本当に難業になってしまった。だが彼らは20代の半ばで本格的に楽器を始めたというやや遅いスタートにも関わらずここまで極めてみせたし、グループの運営方法や音楽性自体他に例えようもない個性的な存在だ。
彼らの旅は今年いっぱいで終わるようだが、彼らが運営するレーベルGuruguru Brainはまだ続きそうだし、中長期的な目線で見ても重要な意味を持つ作品の一つになりそうだ。7月にはフジロックフェスティバル2022への出演を含む最後の凱旋ライヴが国内で行われるらしく、そちらも是非見に行きたい。

.jpg)
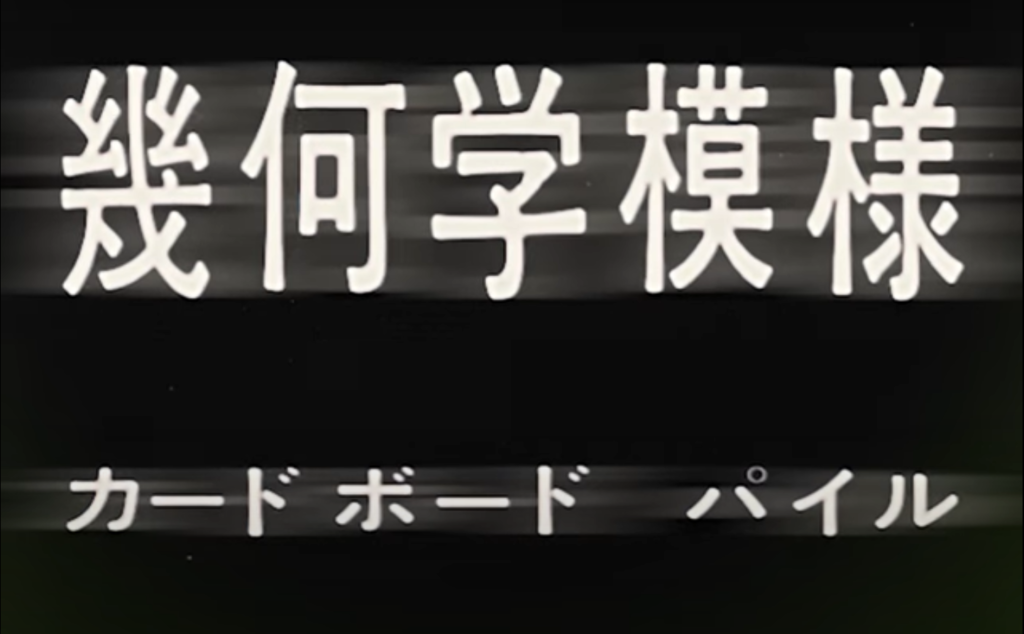
-500x250.jpg)

-500x250.jpg)