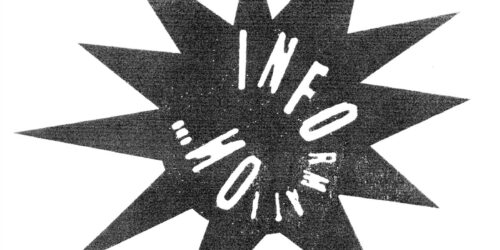Computer Fightと郊外なるもの

Text by Hyozo /野流
「郊外のブルース」というタイトルが示唆するように、スクラップ置き場とカラスという「荒廃した日本」を思わせるアートワークがまずリスナーを峻別する。音楽に純粋なキラキラや反現実を求めているリスナーに用はないとでも言わんばかりのリアリズムの表明。まさにつげ義春イズム。
サウンドについてはどうだろう。切迫感を匂わせるジャンクロックでドライな音像は、トレブリーでアンプの歪みだけだろうという武骨なギターサウンドによって印象付けられているが、それはかつてイクエ・モリが在籍していたアート・リンゼイによるバンド、DNAなどのNo Waveと呼ばれるジャンルやNirvanaの「In Utero」のプロデュースでお馴染みスティーブ・アルビニのグループ、Shellacなどから受け継いだもので、同じくShellacの影響下にあると思われる都内現行グループのTorrなどとも少しサウンドの収斂があるのが興味深い。
ライブではなぜかリアム・ギャラガーの姿勢で歌うやけっぱちなボーカルはミックスや歌唱法のおかげであまり歌詞が聞き取れないが、全体の音像のまとまりを優先した結果かもしれない。
また、基本的にはエモっぽいのだが声質や歌唱法にトリプルファイヤーのようなテイストが見え隠れするので不思議に思ったが、4月(執筆時は2023年)には彼らとの対バン予定もあるようで近いシーンにいることは間違いなさそうだ。
日本語ロック論争から50年の時を経ているが、ロックサウンドと日本語の間に厳然としてある混ざりきらない感覚、それに対する葛藤の有り方、相克の方法はいまだにインディーズ音楽の中で実験され続けている。
演奏は始終タイトで、パワーバイオレンスよろしく矢継ぎ早に短い曲を繰り出し続けるスタイルにはしっかりロックの爽快感もある。
キチッとしたアレンジとドラムプレイも見事で、リズム隊はもしかするとファンクが好きなのかもしれない。とはいえ本物のファンクのような身体性の歓喜、ポリリズムと共に高みへと向かう感覚ではなく、ノリや作曲方法はギターの存在が大きく明確にロック。
また、ノイジーな即興のアプローチもしっかり取り入れている。そこがまたジャパノイズの伝統息づく日本らしい特異性だ。新世代バンドマンには親和性の高いエモやポスト・ブラックメタルからの影響はヴォーカルを除いてあまり感じない。
筆者が千葉県の郊外で育ったこともあり、郊外という概念には格別の思い入れがある。巨大なイオンモール、洋服の青山、焼き肉きんぐ、エネオス、吉野家、デカい公園、庭のない新築、山田うどん、ワンピースの話題、ドンキ、びっくりドンキー、パチスロ、カワチ薬局、自動車の絶えることのない国道、寂れた駅前、家系、スシロー、製鉄所の労働者、ラウンドワン、光化学スモッグ、レッドバロン、顔の濃い中古車貿易商、ハードオフ、タイマッサージ、アコム、ユニクロ、アイフル、業務スーパー、インドネシア生まれのムスリムたち、田んぼ、コンビニ、畑、小学校、幸楽苑、アニメ、コンビニ、しまむら、パキスタン人のカレー屋さん、田んぼ、丸亀製麺、本屋がなくなり、そこに老人ホームが立つ。バラバラのルーツをコンクリートに張り付けて組み上げられた戦後。

これらは日本という大きな村に流れる通奏低音であり、このドローンに適応できない人間は東京に流れ込むしかない。
田舎のイメージがあるブルースというジャンルが実際にはシカゴの都会で生まれた表現であるように、日本の郊外には音楽を生み出し、また聴取する環境がほとんどないからだ。
郊外で耳にする「音楽」といえば、チェーン店で何の意図も空間への配慮もなく無軌道に流れ続ける有線のポップス、蝉、家々から漏れ聴こえるピアノの練習、カラオケ居酒屋の間延びしたリバーブ、線路の軋みに飛行機のジェット、そしてMahel Sharal Hash Buzz(工藤冬里による不定形のユニット、アマチュア感溢れる演奏が特徴)みたいな中学の吹奏楽部と、カラスとヒヨドリのマウント合戦くらいだ。
日本のほとんどの学生は下北沢の高校生よろしくクラブでプロムをやったりしないし、路上でスケボーやサイファーをやれば警察に通報される環境に住んでいる。
漫画やアニメ、ボカロに代表されるような、身体性を排除し、他者とのコミュニケーションを必要としない「弱者の文化」は、この隙間をかいくぐって生まれてきた必然的なものだ。ロックやパンク、ヒップホップでさえリア充的な「強者の文化」になってしまう平和だが屈折した状況。
そういえば一蘭の味集中カウンター(客席が一名ずつセパレートされていて、店員と顔を合わせることさえなくラーメンが出てくるシステム)を10年前に初めて見たとき、高校生の私はそれを大いに歓迎したのだった。「ついに俺の気持ちがわかる飲食店が現れた」と。万人がいち消費者であることで保たれるユートピア、絶え間ない「自分探し」と「自己実現」の連鎖から解放される空間。ひとつ問題があるとすれば食べると絶対に腹が痛くなることだ。
私が育った千葉には四街道ネイチャー(1990年ごろから1998年まで活動、日本語ラップのクラシック的存在)や東金B¥PASS(最近は東金から引っ越したらしい、あのあたりはさすがに不便すぎる)という郊外感を纏ったヒップホップクルーがいくつか存在するが、ヒップホップの専売特許とも言える地元のリアリズムの共有というコミュニケーションを、ロックバンドは今後より追及していくのだろうか。
かつてのめんたいロックや2000年代初頭の北海道のバンドたちを除いては、ローカル性を売りにできるほどの存在は少ないというか、そもそも人口や文化的な意味でそのローカリティを面白がって共有できるリスナーの層が薄すぎ、生まれてもすぐに消えてしまうのかもしれない。

ともあれこの作品は、鋲付き革ジャンや7インチマニアの懐古趣味としてではなく、レベルミュージックとしてかつてパンクが持っていたコアなものを2020年代の日本で結晶させようという意志が感じられる作品だ。
切迫感あふれるがハイ寄りでスカスカした音響と、一切の情緒を排除した甘さのない乾いたイメージ。企業や行政が安易に新海誠の出涸らしのような桜ヒラヒラ、青空キラキラ、JK走る、なんか空飛ぶ「エモい」アニメを作ってマス向けに垂れ流す現状とはまるで正反対だ。
現代において、あらゆる成熟した文化はすぐに資本主義に吸収され、スタイルとして陳腐化する運命にある。かつて「弱者の文化」に見えたものも例外ではない。高いところで美しく輝くものは、その代わりに何か都合の悪いものを隠している。少年たちに夢をチラつかせて何十年も食い物にしていたジャニー喜多川を例に出すまでもない。
蓮の花は臭くて汚い池から咲くものだ。それをひとりひとりが探し出すのがパンクではないだろうか?
このアルバムは平成から令和にかけての日本の郊外という、ある特定の奇妙な文化圏を知る者にとってはある程度腑に落ちる感覚を、それを知らない者には鋭い違和感をもって突き刺さるだろう。また、虚飾やハイプな宣伝も一切似合わない。絶対にメジャーたり得ない表現がここにはあるからだ。
このバンドは中途半端にステージがあるライブハウスというよりは、郊外のイオンの立体駐車場とかでライブを見たいのだが、この先の「郊外」にはそんなイベントがあってもいいと思う。屋外で音を出し、警察を呼ばれる。そんな経験が、本当の意味で民主主義を考えるきっかけになるかもしれないのだから。


.jpg)
-500x250.jpg)