ヴァンダ&ヤングの逆襲 後編

text by Noroi Garcia / DJ, Norogaru Nite
シドニーに戻ったジョージとヴァンダはテッド・アルバートに交渉して自宅近くにスタジオを作る。2人にしてみたら「“金曜日”でたんまり儲けたんだから、それくらいはしてくれよ。」てな具合だろう。
ここを拠点にオーストラリア国内はもとより世界的なヒットを、恐るべきハードワークで量産していく。
それと共にまだ世界のエンタメ界では僻地であったオーストラリアの一レーベル、アルバートプロダクションズの名は国際的に広まっていき、「アルバーツと言えばヴァンダ&ヤング」と両者の名はイコールで結ばれ、制作部門の最高顧問に君臨していく。以下文中に出てくる曲は、注釈がない限り全てヴァンダ&ヤング作、及びプロデュース作品である。
弟達がAC/DCを結成し(レコードデビューは74年、ボーカルはまだボン・スコットではなく後にグラムバンド「Rabbit」を結成するデイヴ・エバンス)その手助けをするかたわら、2人はまずオーストラリア版ゲイリー・グリッターの製造に着手する。
ロンドンでグラムロックムーブメントを間近で見ていた2人にとって、地元で10代に向けたアイドルを売り出そうと考えるのは自然な流れだ。
デビュー曲は出来た。「よし、後は歌入れだ」と思ったら予定していたシンガーがトんでしまう。この曲の高音部を歌いこなせる代役はいないかと、あるクラブ歌手に白羽の矢が立った。悲劇のグラムロックシンガー、William Shakespeareの誕生である(著名な劇作家と同じ芸名でややこしいので国内では、オランダでのクレジット名でもある愛称の“ビリー・シェイク“か本名の“ジョン・ケイヴ“で通っている)。
最幸のグラムポップデビュー曲““Can’t Stop Myself from Loving You”は目論見通り売れた。顔がオッさんなのに(失礼)売れた。10代の少女達は国内の、自分達だけのアイドルを狂おしい程欲していたのだ。
続く2nd、さらに甘味を増したティーンポップ“My Little Angel“は全豪1位にまで到達する。
実はこのシングルのB面に、極上のグラムパンクナンバーが隠れている。
少し話はそれるが、この“Feelin’ Alright”のイントロからAメロは、現代のBovver Rockの旗手(ざっくり言うと、ブーツを踏み鳴らすようなビートが特徴のスレイド直系俗悪ロックンロールの俗称)、イタリアの「Giuda」がデビューアルバム1曲目“Number 10“でそっくりそのまま確信犯的に盗用している。グラムロックレコード蒐集家の作者ロレンゾ・モレッティのこと、「このリフがどこから来たかわかるかい?まだまだ世界には知られていないカッコいい曲があるんだぜ」とカマしとるわけだ。
ここでスター街道をひた走るシェイクスピアに事件がおきる。楽屋に訪ねてきた15歳の少女に手を出したとして有罪判決が下ってしまう。アルバーツとの契約は解消、以降芸能界復帰はならず、晩年は精神疾患とアルコール依存でホームレス状態に。最後は保護施設で息を引き取った。
ある筋の話によれば、これはシェイクスピアに袖にされた少女が腹いせに大騒ぎして親にいいつけ、警察沙汰にした冤罪だったというのが通説だそうだ。
勿論真相は当事者達にしかわからないが、作品に罪は無くデビュー曲は今でも当地で愛され続けている。
次にジョン・ポール・ヤング(以下JPY)のあの曲を紹介しないと気が収まらない。
まだデビュー時の名前が「ジョン・ヤング」だった初期、ヴァンダ&ヤングはまだロンドンにおり、そこで作ったオケを豪に送り、JPYは歌を入れていた。楽曲も本腰を入れて書いたとは思えない軽ポップスで、パッとしないシンガーであった。現地に戻った2人は、このシンガー兼TVタレントを改名させテコ入れを開始する。
75年改名後初シングル“Yesterday’s Hero”(75年)がいきなり大ヒット。このヒットの背景には、JPYがレギュラー出演していたTV番組で繰り返しビデオクリップが流されたおかげもあったようだ。
歌詞の下敷きとなったのは察しのとおり、超人気を誇ったイージービーツ時代の自分達の事で、これもボボボベース作品の傑作だ。
ベイシティローラーズが翌年カバーして、世界中に知れ渡った事は言うまでもないだろう。
次の1stアルバムに先駆けてリリースされた“The Love Game”(75年)はパンチの効いたポップンロールで、このディスコ風ビートは後の特大ヒット“Love Is in the Air(風に舞う恋)”につながっていく。
この曲のビデオクリップに、ミキサー卓の前で楽しそうにはしゃぐ、まだ20代のジョージとヴァンダの姿が終始映し出される。イージービーツ時代を除けば、おそらく2人が並んで動く映像はこれしかないのでないか(あったらごめんなさい)。
そして何といってもベスト盤先行シングルとしてリリースされた“Where The Action Is”(77年)を推さないわけにはいかない。
先導する軽快なピアノ、多幸感溢れるアレンジとコーラスワーク、まるでABBAにElton Johnが加入したかのような夢のナンバーである。
“金曜日の夜、仕事は終わり。ポケットに金は満タン。何処に行くかは風まかせ。確かな事は一つ、何かが始まっているところに俺は行くんだ。眩い光、回るレコード、ロックンロールが一晩中鳴っているところさ。”
まさにThe Weekend Starts Here! 。ヴァンダ&ヤングが若者達に贈った、感動的な週末讃歌だ。

オーストラリア発の最初の世界的ロックスター(「Bee Gees」もいるが、彼等はポップスターと呼ぶべきだろう)、スティーヴィー・ライトも忘れてはならない。
ライトはイージービーツ解散後、音楽活動はしていたものの特筆すべきヒットは生み出せず、一時はアパレルブランドの経営にまで手を出していた。2人は、このヘロイン中毒の治療に苦しむ元同僚のサポートにも乗り出す。
まず復帰第1弾のアルバム『Hard Road』(74年)をプロデュース(ヴァンダ&ヤングの74〜75年の働きっぷりと功績は奇跡としか言いようがない)。3部で構成された曲”Evie“をプレゼントし、これが豪国内では最大級のヒットを記録(世界ではさっぱり)。この曲のPart 1でギターソロを任された、弱冠20歳のマルコム・ヤングはかなり自信がついたそうな。だが、それよりも私はタイトルトラックを聴かせたい。2人が完成させた完璧な重心の低いオージー産パブロックだ。
この曲はもろに「Faces」っぽいからか、ロッド・スチュワートが同年すぐさまカバーしており、ロッドといい(スコットランド家系)ベイシティローラーズ(エジンバラ)といい何か民族的なアンテナで呼応しているのだろう。
そして2ndアルバム『Black Eyed Bruiser』(75年)のタイトルトラックの映像をまずは観て欲しい。
極悪な”You Really Got Me”よろしく、ライトのカッコ良さったらない。天性のパフォーマーなのだ。
良い意味でこのいなたさ満載、オージー産ハードロックの源流を辿っていくと、Billy Thorpe & The Aztecsやロビー・ロイド率いるColoured Ballsに行き着くが、長くなるのでここでは割愛。同じ豪産ハードロックでも、AC/DCにここまでのいなたさや粗暴性はない。逆説的に言えば、最初からマルコム&アンガスのギターワークと楽曲は洗練されていて、ヴァンダ&ヤングはそれを活かしたプロデュースをした、という事だ。
こうしてライトは第2のピークを迎えるのだが、残念ながらそれは2年で終わりを告げる。このアルバム制作時に、ライトは再びヘロインに手を出した事が発覚。アルバーツは契約を強制終了し手を引いてしまう。テッド・アルバート及びジョージとヴァンダは、弟達にも決して近づかせなかった程ハードドラッグが嫌いだったのだ。ヴァンダ&ヤングとライトが再び仕事を共にするのは、「Flash & The Pan」の歌入れに起用する82年まで待たなければならなかった。
ここからは駆け足で。
ヴァンダ&ヤングはその後、70年代後半から80年代にかけて、豪新世代バンド「Rose Tattoo」や「The Angels」(世界デビュー時には「Angel City」に改名)を手掛けていく(プロデュースのみ)。前者のブギーロック、後者の来るべき80’sを予感させるロックは当時10代だった、後のGuns N’ Rosesやグランジ勢のメンバー達に影響を与えた事は周知であろう。
また既に豪EMIでデビューしていた、クリッシー&リンゼイ・ハモンド姉妹のユニット「Cheetah」が80年、アルバーツに移籍してくる。2人はチーター結成前から歌手として活動。クリッシーは75年、ロックミュージカル「ジーザス・クライスト・スーパースター」で共演したメンバーと一緒にあの「Air Supply」を立ち上げた1人だ。
ヴァンダ&ヤングはセクシーな衣装でディスコを歌っていたこの姉妹デュオに、ジーパンとタンクトップを着させイメージを一新させる。マイクスタンドを回し、頭を振り乱してハードロックを歌うその姿は、豪労働者階級の男性達を(そして私も)虜にした。
自分達自身は「Flash &The Pan」というPop Rock〜New Waveユニットを結成(76〜92年)。これまた時代の流行に合わせた作品を作り続け、大成功を収めている。
世界に飛び出してから、当初はセールスに苦労した弟達AC/DCも、ボン・スコットの死を乗り越え20世紀を代表するバンドにまで登り詰めた。ヴァンダ&ヤングは己の才能と力でイージービーツ時代の負の遺産を払拭し、屈強で栄光ある歴史を作り上げたのだ。
晩年、ジョージは亡くなるまでヤング家の資産運用職につき、ヴァンダは息子と音楽プロダクションを作り、レーベルやスタジオ経営をしているそうだ。
最後に。
およそこれからもCD化(今はサブスク化か)は望めないであろうオブスキュアなシングルレコード(主にパンク)を中心に、自分でミキシングして動画サイトに投稿しているmyriverという人物がいる(チャンネル名がmyriver74なので仮にそう呼ぶ事にする)。
前編で紹介したマーカスフックロールバンド“Natural Man”のシングルバージョンを、9年前にいち早くアップしたのはこのmyriver氏だ。私はたまたま知り合いだった氏に、数年前「いつどこでマーカスフックを知ったのか?」と聞いた事がある。氏曰く「きっかけはS山さんですよ。2000年代の真ん中位だったか、針飛びを直してくれと預かった豪コンピ盤に入っていて。それかPure Pop(「Barracudas」のRobin Willsが膨大な量のレコードをレビューしているサイト)で先にインプットされていたのか…どっちが最初だったかもう覚えていない。」。
この「S山さん」とはFink氏(exTeengenerate,現Angel Face,Firestarter)の事である。当のFink氏は「85、86年頃アルバートプロダクションのサンプラー的LPを買ったら”Natural Man”が入っててね。クレジットに“ヴァンダ&ヤング“とあったから、AC/DCに関係したバンドであろうとは思っていた。」と話してくれた。
また私がよく行くロックバーのマスターから「マーカスフックは90年代中頃、友達があの1枚だけ出てる爺さんの絵のLP(『Tales of Old Grand-Daddy』)を買ってきて聴かしてもらった。それで周りのAC/DC好きの奴等にも段々と知られるようになったんじゃないかな。」という話も聞いた。勿論それ以外の例もたくさんあるだろう。
私が片手の操作だけでレアな音源を聴き、マーカスフックロールバンドにたどり着いて、ここまでツラツラと駄文を並べられるのも、全てこういった先人達のガッツある探究心と発掘力、献身的なライフワークのおかげなのである。彼等に最大級の敬意と感謝をここに記しておきたい。
この原稿は故ジョージ・ヤング、マルコム・ヤング、スティーヴィー・ライト、ボン・スコットに捧げます。
最後までお付き合い下さりありがとうございました。

-500x250.jpg)

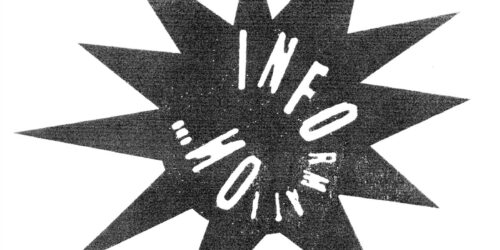

-500x250.jpg)